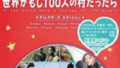友部正人(ともべまさと)の歌の魅力をどう表現したらいいのでしょう。
裸の「たましい」に触れて来る、裸の「たましい」の声とでも言うのでしょうか。
 エディット・ピアフ
エディット・ピアフ
今なら友部正人に同じ讃辞を贈りたいです。
この人たちは、日常の何気ない一コマを歌う中に、たとえ電話帳にある人名を読み上げるだけでも、その人々の持つ悲しみや歓びを限りなく注入することができました。だからどんな歌を歌っても、ピアフ同様友部も市井の人々の側に、民衆の側に立っています。
とは言うものの、西洋音楽至上主義という病に長い間冒されてきた僕が、友部の歌を聴いたのは、恥ずかしいことに中年になりかけたころなのです。
僕の友人に、ボストンのバークレイ音楽院に入学し、理論的なものに偏るつまらなさを感じて退学、その後当時のアメリカ・ブラック・ジャズ界随一のテナー・サックス奏者デイヴィッド・S・ウェアに弟子入りしたサックス吹きがいました。まだ25~26歳だったと思います。
様々なジャンルの音楽に対する感性が豊かで、「じゃがたら(JAGATARA)」(注1)やマーク・リボー(注2)、あがた森魚の「雷蔵」(注3)なんかは彼から教えてもらいました。彼と音楽の話をするのは楽しみでした。
ある日、僕は彼にこう聞きました。
「妻の友人で、友部正人っていうのがいるんだけど、昨日コンサート行ったんだ。友部正人って知ってる?」
すると彼は即座にこう答えました。
「知ってますよ、あの字余りの方でしょ」
「えーっ、やっぱり知ってる?」
「知ってますよ、あの人は本物ですよ」
彼に言わせると、70年代のフォーク歌手の多くが生き易い方に流されていった中で、友部は自分の本当に歌いたいものを貫き通していった本物なんだそうです。彼の言葉のはしばしから、同じ音楽を志すものとして友部正人を尊敬している様子が伺い知れました。
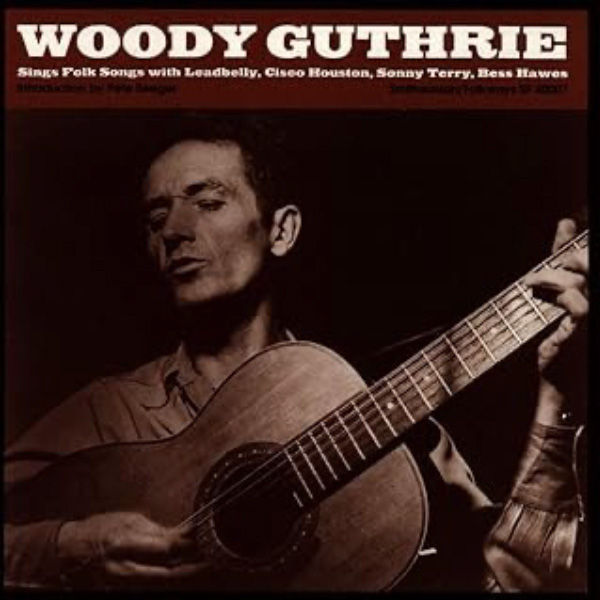 『Woody Guthrie Sings Folk Songs』
『Woody Guthrie Sings Folk Songs』
Smithsonian Folkways 1944~
高校時代を愛知県で過ごし、ビートルズのコピーバンドをしたりしていましたが、ボブ・ディランの「ライク・ア・ローリング・ストーン」を聴いて衝撃を受け、ソング・ライティングを志し、アメリカのフォーク歌手ウディ・ガスリーやレッド・ベリーらのように民衆の感情を歌いたいと思い、路上で歌い始め、やがて大阪に移住します。
西岡恭蔵、大塚まさじ、高田渡らと交流しながら、1969年に京都フォークキャンプ、1971年には武蔵野タンポポ団のメンバーとして中津川フォークジャンボリーに参加、1972年に『大阪へやって来た』で衝撃的なレコード・デビュー、1973年には「一本道」を含む初期の代表作『にんじん』を発表します。
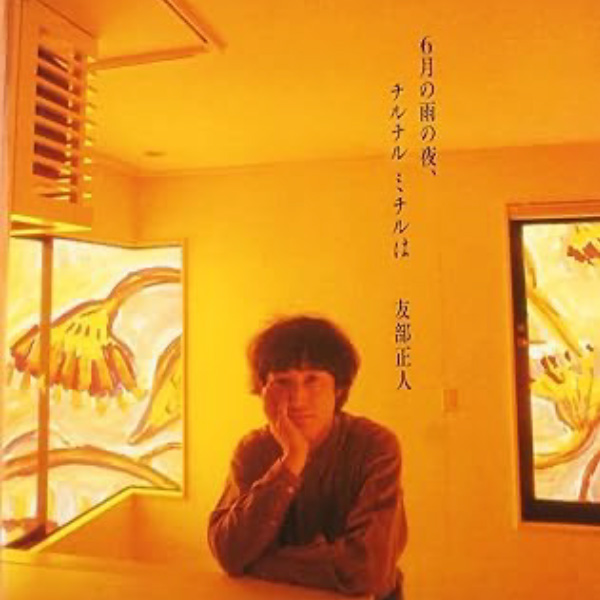 『6月の雨の夜、チルチルミチルは』
『6月の雨の夜、チルチルミチルは』
友部正人オフィス 1987
タイトル曲はアコースティックな柔らかい、シンプルだが色彩豊かなバックに乗って、小節線を超えて自分の思いを語り出していきます。
もちろんボブ・ディランの影響は大きいのでしょうが、僕には「歌」というより音楽に乗せた詩の朗読のように思われてなりません。
歌詞の語尾の母音が「なのにぃ~」とか「のすがたでぇ~」と伸びてゆくところなど、「たましい」まで友部の喉から飛び出して来そうで胸が熱くなりますし、日本の「語り物」と呼ばれる音楽の伝統も継いでいるように思えます。
そして、その詩の美しさたるや。
「知らないことで真んまるなのに、知ると欠けてしまうものがある」という一節があります。
アメリカのカウンター・カルチャーの中で、若者に愛されていたシェル・シルヴァスタインの「自分という存在」についての絵本『ぼくを探しに』(注4)を丸々読んだような気分にしてくれます。(注5)
そして最後の曲が、彼の歌の中で僕が一番好きな「愛について」。
ピアノとベース、チェンバロのゆったりとしたリズムに乗って彼が歌っていくのですが、「語り」を続けているうちにどんどん思いが深まり、高まり、友部正人によってしか体験できない唯一無二の世界へと連れていかれます。最後の歌詞の余韻の深さと言ったら。
中国の長編詩の朗読を聴いているとこんな感じなのだろうか、ビート詩人アレン・ギンズバーグの『吠える』(注6)だったら、そう谷川俊太郎の名作『生きる』(注7)を音楽に乗せて歌ってくれたら、こんな感じなのだろうかと思います。谷川俊太郎が友部正人の大ファンだったのも納得です。(注8)
その歌の魅力をもう少し考えてみたいと思います。
2025.2.25
(注2)アメリカのフリー・ジャズ・ギタリスト(1954~)。ジミ・ヘンドリクス、ビートルズ、デューク・エリントンからキューバ音楽、第2次世界大戦後の反戦歌までを縦横無尽に横断しています。
(注3)あがた森魚が、元じゃがたらのOTOらと1990年に結成したユニット。翌年発表された『雷蔵参上』では、アルジェリアの「ライ」からインドネシアの「クロンチョン」まで、ワールド・ミュージックとシンクロした非常に刺激的な音楽を聴かせました。
(注4)1976年発表、日本語訳は倉橋由美子。

(注5)https://www.youtube.com/watch?v=qFnE7-1yjJ8 パスカルズとのライヴ 2006年
(注6)1956年発表のビートニク文化を代表する作品。
「僕は見た 狂気によって破壊された僕の世代の最良の精神たちが 飢え 苛ら立ち 裸で夜明けの黒人街を腹立たしい一服の薬を求めて のろのろ歩いてゆくのを
夜の機械の 星々のダイナモとの 古代からの神聖な関係を憧れてしきりに求めている天使の頭をしたヒップスターたち・・・・・」
(注7)1971年発表。
「生きているということ いま生きているということ
それはのどがかわくということ 木もれ陽がまぶしいということ
ふっと或るメロディを思い出すということ くしゃみすること
あなたと手をつなぐこと・・・・・」
(注8)https://www.youtube.com/watch?v=4ZaPHnY5HqQ 弾き語りのライヴ 2006年